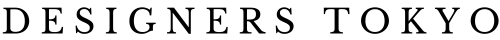オフィス・事務所の契約|敷金の相場を解説

オフィスや事務所を構える際、敷金の支払いが大きなハードルとなることは珍しくありません。
特に初めてのオフィス開設や事務所移転の際には、敷金の相場やその他の費用がどれくらいになるのか、予算計画に大きく影響するでしょう。
また、退去時には敷金がどの程度戻ってくるのか、その計算方法や条件についても不安を感じる方が多いのではないでしょうか?
本記事では、これらの敷金に関わる疑問を解消し、賢くコストを抑える方法を解説します。 賃貸契約において重要な敷金と保証金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?まず以下の基本を確認しましょう。
賃貸契約において重要な敷金と保証金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?まず以下の基本を確認しましょう。
ここでは、敷金と保証金の基本事項について解説します。
例えば、部屋を退去する際に原状回復が必要な場合、敷金から費用が差し引かれ、また、契約終了時に未払いの賃料がある場合、敷金が充てられます。
敷金は賃借人にとっては大きな出費ですが、物件を守るための保証として一般的です。
貸主は、敷金から滞納賃料分を直接差し引くことが可能です。また、修繕費についても敷金を利用した支払いが一般的ですが、テナントとの事前の合意が必要になる場合があります。
特に大きな修繕が必要なとき、その費用が敷金の範囲を超える可能性もあり、追加の支払いが求められる場合もこともあります。
賃貸契約を結ぶ際は、敷金でまかないきれないケースにどう対応するか事前に検討しておきましょう。
参照:民法第六百二十二条の二 │ e-Gov法令検索
関西には礼金の慣習がない場合が多く、保証金+敷引き〇ヶ月(保証金を返還する際に必ず引かれるお金)というケースが多くありました。実質的にはオーナーの礼金変わりとなってます。
ここでは、オフィスや事務所の敷金相場について解説します。
また、賃借人が契約終了時に物件を元の状態に戻さなかった場合、敷金から修繕費が差し引かれますが、無事に物件を綺麗な状態で返却できれば、敷金は全額または一部返金が期待できます。
一般住居の敷金は比較的低めであるため、個人の負担も大き過ぎることはありません。
小規模なオフィスであれば3〜6ヶ月分の敷金が一般的ですが、面積が広い場合は6ヶ月から12ヶ月分の敷金が求められることが多いです。
例えば、50坪以上のオフィスでは、高い保証金が設定される傾向にあります。大きな敷金が必要になる背景には、大規模な修繕や損害が発生した時の高額な修繕費用をカバーするためです。
賃借面積が広ければ広いほど、その分リスクも大きくなるため、敷金の額も増加します。
オーナーとしては、将来的に発生可能なコストを前もって確保しておく必要があり、それが敷金に反映されています。
一概には言えませんが、個人オーナーの場合は、3〜6ヶ月分、大手デベロッパーが管理するオフィスでは、6〜12ヶ月分の敷金というケースが多いです。
大手デベロッパーが管理する物件は、一般に設備が整っており、また保守管理もしっかりしているため、その分敷金が高いです。また、大手の場合、物件に対する責任をしっかりと持つために高額の敷金を設定する場合もあります。 オフィスや事務所の敷金が、一般的な住居の敷金より高い理由は以下のとおりです。
オフィスや事務所の敷金が、一般的な住居の敷金より高い理由は以下のとおりです。
ここでは、オフィスや事務所特有の、敷金が高くなる背景を解説します。
オフィススペースは多くの場合、テナントによるカスタマイズが行われるため、退去時には元の状態に戻すための費用も大きくなります。
例えば、壁の追加や特殊な床材の使用など、改装された内装を原状に戻す作業は複雑で高価です。
また、オフィス機器や設備の取り外しには専門的な技術が必要で、これらの作業には相応のコストが発生します。
高い敷金は、このような費用に対する保障として機能しています。
オフィスビルの賃料は一般住居のと比較して格段に高額であり、そのため賃料の未払いが発生した際の影響も大きくなります。
未払いがあると、オーナーは即座に経済的な打撃を受け、ビルの運営に必要な資金が不足することになります。
敷金を高く設定すればこのようなリスクを前もってカバーし、賃借人が賃料を滞納した場合でも、影響を最小限に抑えることが可能です。
加えて、高額な賃料による未払いは法的な手続きを伴うことが多く、その過程で発生する費用も敷金から充当できます。
このように、敷金は未払いリスクの高さも反映しています。
ここでは、敷金がどの程度返還されるか、また、より多くの敷金を戻してもらう方法について解説します。
一般的に、物件を使用した後の通常の摩耗を超える損傷があった場合、修復に必要な費用は敷金から原状回復費用として差し引かれます。
また、敷金の一部が事前に定義された「償却(敷引)」として設定されている場合、これも返還されません。
敷金の返還額は退去時の物件の状態に大きく左右されるため、敷金の返還を期待するなら、日頃から物件を丁寧に扱わなければなりません。
償却費は、貸主に対する礼金であったり、更新料が免除された場合にはその謝礼として位置づけられており、通常、無条件に差し引かれて返還はされません。
一方、原状回復費は退去時に物件を初期状態に戻すために必要な費用で、壁のペイントや床材の交換などが含まれます。原状回復費用はオフィスの規模や、オフィスビルのグレードなどによって異なるため、費用相場は坪単価5万円〜20万円と開きがあります。
退去時には、自分でできる範囲の清掃や小修理を行い、貸主の評価を良くする努力も必要でしょう。また、原状回復は建築不動産の知識が無いと内容の精査ができません。
適正な価格で工事発注できるよう専門家に相談する事もお勧めします。
「お問い合わせ」はこちら
ここでは、原状回復費用を抑えるポイントを紹介します。
指定業者作成の原状回復の見積には、原状回復範囲外の工事、つまり賃借人がお金を出さなくても良い工事が含まれていることがあり、これは中々見抜く事ができません。工事単価や数量、原状回復範囲の適正査定をすることにより、原状回復費用が大きく削減出来たというケースも多くございます。
交渉時には、具体的な修繕箇所や費用の詳細を事前にリストアップし、その上でどの点について費用を抑えるかを中心に話を進めるとよいでしょう。但し、
入居時に原状回復工事の取り決めがされているケースも多いため、退去時に慌てるのではなく、契約時にしっかりと確認しておきましょう。
居抜き退去とは、退去時に内装や設備をそのままにして出ることで、次の入居者が、費用を抑えつつ設備をそのまま利用できるメリットがあります。
居抜き退去をする場合、壁の塗り替えや床の張り替えなどのコストがかからないため、原状回復費用をほとんど支払う必要がなくなる場合が多いです。
ただし、この方法を選択する場合は、事前に貸主の同意を得なければなりません。
オフィス・事務所の敷金の相場は、賃借面積やオーナーの種類によって異なりますが、およそ賃料の3〜12ヶ月分で一般住居の賃貸より高額です。
オフィス・事務所の敷金は退去時に通常は返還されますが、償却費や原状回復費が差し引かれます。原状回復費用を抑えればより多くの敷金の返還が期待できるため、長期的な契約を想定していない場合は、原状回復費用を抑えるためにできるだけ修繕費用が発生しない使用に努めなければなりません。原状回復費を抑えるには、専門家に相談したり、貸主との交渉、居抜きで退去することが有効です。
最近は、敷金や初期費用を抑えた物件、退去時のコストまで抑えた物件、拡張などの成長フェーズにあわせ移転をスムーズに出来る物件も増えてきています。
魅力的な敷金0物件や、原状回復不要物件なども当社では多く取り扱っております。
おしゃれでカッコいい賃貸オフィス、機能的で快適な空間のデザインオフィスなど、東京のセットアップオフィス、居抜きオフィスをお探しなら、デザイナーズ東京まで是非ご相談ください。貴社の物語を彩る素敵なワークプレイスを一緒に見つけましょう。
「敷金0」はこちら
「初期安」はこちら
「セットアップオフィス」はこちら
「物件一覧」はこちら
「お問い合わせ」はこちら
特に初めてのオフィス開設や事務所移転の際には、敷金の相場やその他の費用がどれくらいになるのか、予算計画に大きく影響するでしょう。
また、退去時には敷金がどの程度戻ってくるのか、その計算方法や条件についても不安を感じる方が多いのではないでしょうか?
本記事では、これらの敷金に関わる疑問を解消し、賢くコストを抑える方法を解説します。
敷金・保証金とは?
 賃貸契約において重要な敷金と保証金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?まず以下の基本を確認しましょう。
賃貸契約において重要な敷金と保証金とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?まず以下の基本を確認しましょう。- 敷金・保証金は契約時に支払う預託金
- 賃料の滞納、修繕費に充当
- 敷金・保証金の違い
ここでは、敷金と保証金の基本事項について解説します。
敷金・保証金は契約時に支払う預託金のこと
敷金は、契約時にテナントがオーナーに支払う重要な預託金で、賃貸契約において発生する可能性のある損害や滞納をカバーするためのものです。例えば、部屋を退去する際に原状回復が必要な場合、敷金から費用が差し引かれ、また、契約終了時に未払いの賃料がある場合、敷金が充てられます。
敷金は賃借人にとっては大きな出費ですが、物件を守るための保証として一般的です。
賃料の滞納、修繕費に充当
賃料が滞納された場合や、賃貸物件が何らかの理由で損傷した場合、オーナーは敷金を使用して問題を解決します。貸主は、敷金から滞納賃料分を直接差し引くことが可能です。また、修繕費についても敷金を利用した支払いが一般的ですが、テナントとの事前の合意が必要になる場合があります。
特に大きな修繕が必要なとき、その費用が敷金の範囲を超える可能性もあり、追加の支払いが求められる場合もこともあります。
賃貸契約を結ぶ際は、敷金でまかないきれないケースにどう対応するか事前に検討しておきましょう。
参照:民法第六百二十二条の二 │ e-Gov法令検索
敷金・保証金の違い
敷金と保証金はしばしば混同されがちですが、「保証金」は、関西など西のエリアで使われることが多い言葉で、基本的には「敷金」と同様の意味を持ち、滞納があった場合に備えるものとしてオーナーに支払う預託金です。関西には礼金の慣習がない場合が多く、保証金+敷引き〇ヶ月(保証金を返還する際に必ず引かれるお金)というケースが多くありました。実質的にはオーナーの礼金変わりとなってます。
オフィス・事務所の敷金相場はいくら?
一般的な住居のための賃貸の敷金については多くの方が経験的に「このぐらい」という相場観をもっていますが、オフィスや事務所の敷金相場はどれくらいなのでしょうか?以下の順に見ていきましょう。- 一般住居は賃料の1〜2ヶ月分
- 賃借面積で見るオフィス・事務所の敷金相場
- 貸主で見るオフィス・事務所の敷金相場
ここでは、オフィスや事務所の敷金相場について解説します。
一般住居は賃料の1〜2ヶ月分
一般住居の賃貸の敷金は、賃料の約1〜2ヶ月分が一般的で、物件の損害や修繕が必要な場合に使用されるための保証金として機能します。また、賃借人が契約終了時に物件を元の状態に戻さなかった場合、敷金から修繕費が差し引かれますが、無事に物件を綺麗な状態で返却できれば、敷金は全額または一部返金が期待できます。
一般住居の敷金は比較的低めであるため、個人の負担も大き過ぎることはありません。
賃借面積で見るオフィス・事務所の敷金相場
オフィスや事務所の敷金相場は、賃借面積によって大きく変わります。小規模なオフィスであれば3〜6ヶ月分の敷金が一般的ですが、面積が広い場合は6ヶ月から12ヶ月分の敷金が求められることが多いです。
例えば、50坪以上のオフィスでは、高い保証金が設定される傾向にあります。大きな敷金が必要になる背景には、大規模な修繕や損害が発生した時の高額な修繕費用をカバーするためです。
賃借面積が広ければ広いほど、その分リスクも大きくなるため、敷金の額も増加します。
オーナーとしては、将来的に発生可能なコストを前もって確保しておく必要があり、それが敷金に反映されています。
貸主で見るオフィス・事務所の敷金相場
敷金の相場は貸主のタイプによっても大きく異なります。一概には言えませんが、個人オーナーの場合は、3〜6ヶ月分、大手デベロッパーが管理するオフィスでは、6〜12ヶ月分の敷金というケースが多いです。
大手デベロッパーが管理する物件は、一般に設備が整っており、また保守管理もしっかりしているため、その分敷金が高いです。また、大手の場合、物件に対する責任をしっかりと持つために高額の敷金を設定する場合もあります。
オフィス・事務所の敷金が一般住居よりも高いのはなぜ?
 オフィスや事務所の敷金が、一般的な住居の敷金より高い理由は以下のとおりです。
オフィスや事務所の敷金が、一般的な住居の敷金より高い理由は以下のとおりです。- 原状回復費用が高くつきやすい
- 賃料が高く未払いリスクが高い
ここでは、オフィスや事務所特有の、敷金が高くなる背景を解説します。
原状回復費用が高くつきやすい
オフィスの敷金が一般住居より高い主な理由の一つは、オフィス・事務所の方が原状回復費用が傾向として高額だからです。オフィススペースは多くの場合、テナントによるカスタマイズが行われるため、退去時には元の状態に戻すための費用も大きくなります。
例えば、壁の追加や特殊な床材の使用など、改装された内装を原状に戻す作業は複雑で高価です。
また、オフィス機器や設備の取り外しには専門的な技術が必要で、これらの作業には相応のコストが発生します。
高い敷金は、このような費用に対する保障として機能しています。
賃料が高く未払いリスクが高い
オフィスの敷金が一般住居と比べて高いもう一つの理由は、賃料自体の高さとそれに伴う未払いリスクです。オフィスビルの賃料は一般住居のと比較して格段に高額であり、そのため賃料の未払いが発生した際の影響も大きくなります。
未払いがあると、オーナーは即座に経済的な打撃を受け、ビルの運営に必要な資金が不足することになります。
敷金を高く設定すればこのようなリスクを前もってカバーし、賃借人が賃料を滞納した場合でも、影響を最小限に抑えることが可能です。
加えて、高額な賃料による未払いは法的な手続きを伴うことが多く、その過程で発生する費用も敷金から充当できます。
このように、敷金は未払いリスクの高さも反映しています。
退去時にオフィス・事務所の敷金はいくら返ってくる?
退去時の敷金はどれくらい返還されるのでしょうか?敷金と返還される金額について以下を確認しましょう。- 全額返還は基本的にない
- 償却費・原状回復費が差し引かれる
- 多く返還してもらうには、原状回復費を抑える
ここでは、敷金がどの程度返還されるか、また、より多くの敷金を戻してもらう方法について解説します。
全額返還は基本的にない
オフィスや事務所の敷金で全額返還されるケースは非常に稀です。一般的に、物件を使用した後の通常の摩耗を超える損傷があった場合、修復に必要な費用は敷金から原状回復費用として差し引かれます。
また、敷金の一部が事前に定義された「償却(敷引)」として設定されている場合、これも返還されません。
敷金の返還額は退去時の物件の状態に大きく左右されるため、敷金の返還を期待するなら、日頃から物件を丁寧に扱わなければなりません。
償却費・原状回復費が差し引かれる
退去時に敷金から差し引かれる主な費用は、償却費と原状回復費です。償却費は、貸主に対する礼金であったり、更新料が免除された場合にはその謝礼として位置づけられており、通常、無条件に差し引かれて返還はされません。
一方、原状回復費は退去時に物件を初期状態に戻すために必要な費用で、壁のペイントや床材の交換などが含まれます。原状回復費用はオフィスの規模や、オフィスビルのグレードなどによって異なるため、費用相場は坪単価5万円〜20万円と開きがあります。
多く返還してもらうには、原状回復費を抑える
敷金をより多く返還してもらうためには、原状回復費を抑える必要があり、契約期間中、可能な限り摩耗や損傷を避けるように物件を慎重に使用するよう努めなければなりません。退去時には、自分でできる範囲の清掃や小修理を行い、貸主の評価を良くする努力も必要でしょう。また、原状回復は建築不動産の知識が無いと内容の精査ができません。
適正な価格で工事発注できるよう専門家に相談する事もお勧めします。
「お問い合わせ」はこちら
原状回復費用を抑えるポイント
原状回復費用を抑えれば、返ってくる敷金も多くなります。以下の原状回復費用を抑えるポイントを検討しましょう。- 専門家に依頼する
- 貸主と交渉する
- 居抜きで退去する
ここでは、原状回復費用を抑えるポイントを紹介します。
専門家に依頼する
原状回復費用を抑えるためには、先述した専門家への依頼を検討しましょう。指定業者作成の原状回復の見積には、原状回復範囲外の工事、つまり賃借人がお金を出さなくても良い工事が含まれていることがあり、これは中々見抜く事ができません。工事単価や数量、原状回復範囲の適正査定をすることにより、原状回復費用が大きく削減出来たというケースも多くございます。
貸主と交渉する
原状回復に際しては、貸主との交渉が重要です。特に、敷金から差し引かれる修繕費用の範囲や条件について明確に話し合い、合理的な合意を形成するように心がけてください。貸主と良好な関係を築きながら交渉を進めれば、敷金の全額返還は難しいものの、可能な限り多くの返還を目指せます。交渉時には、具体的な修繕箇所や費用の詳細を事前にリストアップし、その上でどの点について費用を抑えるかを中心に話を進めるとよいでしょう。但し、
入居時に原状回復工事の取り決めがされているケースも多いため、退去時に慌てるのではなく、契約時にしっかりと確認しておきましょう。
居抜きで退去する
居抜きでの退去は、原状回復費用を大幅に削減する手段として有効です。居抜き退去とは、退去時に内装や設備をそのままにして出ることで、次の入居者が、費用を抑えつつ設備をそのまま利用できるメリットがあります。
居抜き退去をする場合、壁の塗り替えや床の張り替えなどのコストがかからないため、原状回復費用をほとんど支払う必要がなくなる場合が多いです。
ただし、この方法を選択する場合は、事前に貸主の同意を得なければなりません。
敷金を抑えたオフィス・事務所の契約のことなら、まずはご相談を
本記事では、オフィスや事務所の敷金に関するさまざまな疑問に対して解説してきました。オフィス・事務所の敷金の相場は、賃借面積やオーナーの種類によって異なりますが、およそ賃料の3〜12ヶ月分で一般住居の賃貸より高額です。
オフィス・事務所の敷金は退去時に通常は返還されますが、償却費や原状回復費が差し引かれます。原状回復費用を抑えればより多くの敷金の返還が期待できるため、長期的な契約を想定していない場合は、原状回復費用を抑えるためにできるだけ修繕費用が発生しない使用に努めなければなりません。原状回復費を抑えるには、専門家に相談したり、貸主との交渉、居抜きで退去することが有効です。
最近は、敷金や初期費用を抑えた物件、退去時のコストまで抑えた物件、拡張などの成長フェーズにあわせ移転をスムーズに出来る物件も増えてきています。
魅力的な敷金0物件や、原状回復不要物件なども当社では多く取り扱っております。
おしゃれでカッコいい賃貸オフィス、機能的で快適な空間のデザインオフィスなど、東京のセットアップオフィス、居抜きオフィスをお探しなら、デザイナーズ東京まで是非ご相談ください。貴社の物語を彩る素敵なワークプレイスを一緒に見つけましょう。
「敷金0」はこちら
「初期安」はこちら
「セットアップオフィス」はこちら
「物件一覧」はこちら
「お問い合わせ」はこちら